「女性とスポーツ」
老若男女を問わない国民的なスポーツ・ブームの中で、女性のスポーツ領域における進出、活躍には目覚ましいものがあります。一方、女性の生理機能は極めて微妙な機構によって調節されていますが(図1)、その働きが未熟で発達段階にある思春期では、スポーツが生理機能の正常な成熟過程に及ぼす影響、さらに身体発育に与える影響について、配慮が必要となります。そこで、まず最初に、スポーツが女性の生理機能にどのように、影響するかを簡単に紹介します。
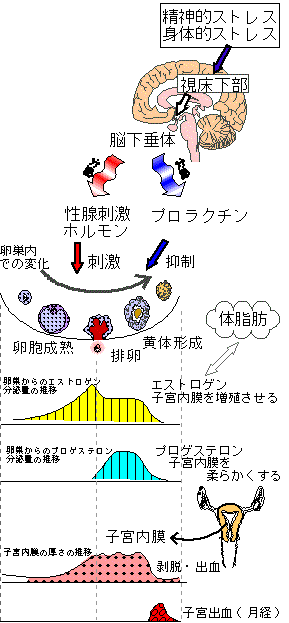 |
1.スポーツと初経発来
初経は年齢に関わらず、体重が43Kg位になると発来します。これは、卵巣の働きが体脂肪と関係するためです。そのため、初経発来以前から激しいトレーニングを開始したり、ウエイト・コントロールを行うと初経発来が遅れます。最近の初経年齢は10歳から14歳位が多いので、
16歳になっても初経を迎えない場合には検査が必要です。
2.スポーツと月経の性状
日常的なスポーツ活動は月経の持続日数と経血量には影響しません。月経随伴症状としての下腹痛や腰痛などの月経痛は、スポーツ活動によって骨盤内のうっ血がとれることで軽快することが知られています。しかし、スポーツ選手では、一般の女性と比べて排卵を伴わない月経の率が高く、この場合には月経痛が軽微であることから、スポーツによって月経痛が軽快したときは無排卵周期に移行している場合がありますので、排卵の有無について基礎体温をチェックしておくことが必要です。
|
3.スポーツと内分泌機能
激しいスポーツ活動が内分泌機能に対してどのような影響を及ぼすかについては次のようなことが分かっています。
a.短期的影響
激しいスポーツ活動時には、プロラクチンが著明に上昇します。このホルモンは脳下垂体から分泌され、乳腺での乳汁産生を刺激する他、様々な作用をしますが卵巣の働きについては、それを抑制する方向に作用します。
b.長期的影響
テストステロン(男性ホルモン)に変化はありませんが、エストロン、エストラジオールといった女性ホルモンは著しく減少します。脳下垂体から分泌される性腺刺激ホルモンも低下していて、視床下部にある性ホルモン中枢の機能異常が考えられています。
これらのデータは、激しいスポーツ活動時のものですが、通常のスポーツ活動においても程度の差はあれ、同様の変化は起こっているものと考えられます。このようなホルモン環境の変化に加えて、体脂肪の減少、さらには、家庭環境や学校状況から生じる種々の精神的・身体的ストレスが要因となって、各種の月経異常が発現してきます。(図1)その中で、特に注意が必要な状態を二つあげます。
①機能性子宮出血(図2-a)
多くは無排卵性の月経周期に起因したものです。排卵には至らないものの、ある程度の卵胞発育がみられ、そこから分泌されるエストロゲンによって子宮内膜が増殖してゆき、エストロゲンの量との関係で不規則に剥脱・出血してきます。この時、剥がれ落ちない内膜が次第に子宮内に蓄積していくことが時にみられ、この場合はいずれ、子宮からの大量出血をきたします。 月経周期は不規則であっても、月経の持続日数が7日以内で、かつ、経血量の増加がなければまず問題ありません。月経の持続日数が段々と長くなってきたり、経血量が次第に増えてくるような時は、貧血を招来したり、また、突然の大出血で身体的・精神的に大きなダメージを被ってしまうことがありますので、早めに検査を受けておく方が安心です。
②続発性無月経(図2-b)
初経後に、6ヵ月以上も月経の無い状態を続発性無月経といいます。排卵はなく、また、卵胞発育もないためにエストロゲンが分泌されず、子宮内膜の増殖が停止します。
スポーツ活動に起因するものは一過性の機能失調であり、大抵の場合、自然に回復します。もし長期間放置して無月経期間が長くなると、排卵周期の回復が困難になります。
無月経期間は子宮が徐々に萎縮してゆくため、思春期の長期の無月経は、子宮の発育不全を招来し、将来妊娠しにくくなる恐れがあります。
また、無月経は、体内のエストロゲンが低下しているということのひとつの表れですが、女性が女性らしくあるためにはエストロゲンが不可欠です。さらに、エストロゲンは悪玉コレステロールを排除したり、血管内皮を保護してくれます。
骨粗髪症の予防には30歳までにしっかりとした骨を作っておくことが大切ですが、エストロゲンは骨量の維持にも大切な働きをしています。エストロゲンの低下した状態が6ヶ月を越えなければ大きな問題にはなりませんが、健康への影響を考えると少しでも早い対応が必要です。
また、この無月経について考える時、常に妊娠の可能性を念頭に置くことが大切です。
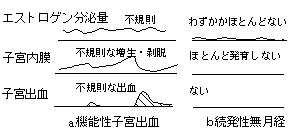 |
| 図2 月経異常 |
4.月経周期とコンディション
健康維持に役立つスポーツですが、体調に注意して行わないと事故につながる恐れがあります。女性のコンディショニングを考える場合、一般的なコンディションばかりでなく、月経周期の時期との関係も重要です。
自覚的にコンディションが良いと感じられるのは、月経と月経の中間期と、月経後1週間位の時期です。これに対して、コンディションの悪い時期は月経期間中と、月経前1週間位です。(図3)試合などに際して、コンディションの悪い時期を避けるために月経を移動させることができます。これには、月経周期短縮法と延長法がありますが、前者の方が有利です。実際には産婦人科医に相談して2ヵ月位前に調節しておくのが安全です。
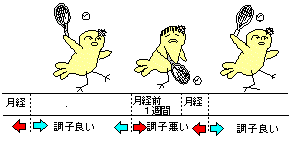 5.月経時のスポーツ活動
5.月経時のスポーツ活動
非常に激しいスポーツ活動は出血量を増加させることがあるので、月経時には避けるべきでしょう。しかし、通常のスポーツ活動は特に重大な障害はありません。普段と同じようにして支障はありませんが、出血と月経痛に対しては配慮が必要です。
a.タンポン法
現在では、清潔に包装されたものが数種類あり、自分にあったものを使用することで、月経中であっても水泳をはじめ、各種スポーツを行っている女性は少なくありません。ただし、タンポンは感染の危険性を伴うので、清潔な取扱いを心掛けること、そして8時間以上、挿入したままにしないことが大切な点です。
自分の性器の構造に対する知識に乏しく、性器に手を触れることに抵抗感のあるときには、その使用にかなり困難を伴いますが、タンポンの持つ機能や使用法を誤ることなく、月経の進みぐあいや経血量、あるいはスポーツ活動などの行動予定と合わせて、うまく使えるように指導できれば理想的だといえます。
b.月経痛
基本的な注意は、下半身を冷やさないことです。日頃からスポーツに親しみ、月経期間中にも無理の無い程度に体を動かすことは月経痛の軽減に有効です。活動が制限されるような痛みに対しては、鎮痛剤を早めに服用することが大切です。痛みは我慢すべきものではありません。我慢していると段々と生理痛に対して過敏になり、益々つらく、そして、自分の女性性に対してネガティブな感情を育ててしまいます。月に一度、数日間鎮痛剤を使用しても、その副作用はまず心配ありません。月経痛が以前と比べて次第に重くなってきたり、鎮痛剤の効きめが無くなってきたような時は、子宮内膜症や骨盤内の感染症など、治療が必要なこともありますので検査を受けた方が良いでしょう。
おわりに
スポーツ活動が生理機能に及ぼす影響と、それと関連する異常状態について概説しました。これらの異常は実際には、スポーツ活動と無関係に発生することの方が圧倒的に多く、一方で、スポーツ活動によってもたらされる恩恵はここで改めてあげる必要も無いくらい明白なものです。月経異常をきたすことがあり得るといって、決してスポーツ活動を否定するものではありません。日常的なスポーツ活動による健康管理、増進は極めて好ましいものです。しかし、場合によっては生理機能や身体発育に障害をおこし得ることを知ることが、細心な健康管理のためには必要です。また、女性の生理機能を知ってこそコンディショニングや快適なスポーツ活動が可能になります。
目次に戻る
静岡市医師会健康スポーツ医学委員
産婦人科 深澤 洋幸
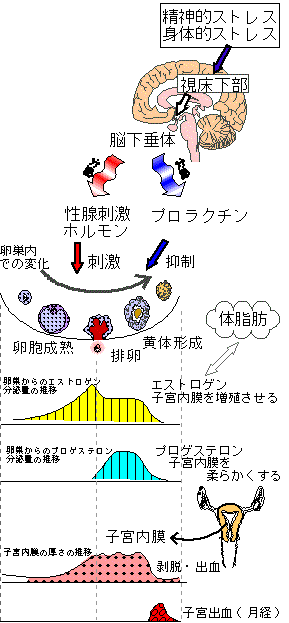
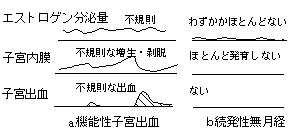
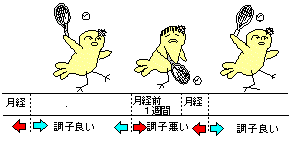 5.月経時のスポーツ活動
5.月経時のスポーツ活動